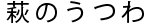十六世紀末期の文禄・慶長の役(1592~1598)による豊臣秀吉の朝鮮出兵において毛利輝元はその総師として渡海し、李朝有数の窯産地「鶏竜山」から萩焼の開祖李勺光、李敬を招致しました。
慶長5年(1600)関ヶ原の役に敗北した輝元は長門・周防二箇国三十六万石に削封され、慶長9年(1604)萩に入府しました。それに伴い李勺光一統は城下の東郊松本村中之倉(現萩市椿東中の倉)に漸次窯を構築し、その半世紀後には大津郡深川村三之瀬(現・長門市深川湯本三之瀬)にも分窯。江戸時代を通じて萩(毛利)藩の御用窯として繁栄し、現在に至っていますが、南朝鮮李朝前期の様式を色濃く伝承する茶陶として発展しています。元々萩の地域は古くから良質の陶土に恵まれており、現在の萩市小畑地域はその昔「埴田」と称していました。また、「延喜式」に見られる「長門須恵器」の一産地として推定されており、古くから窯業地帯であったと考えられています。そのような歴史的風土に加えて、輝元をはじめとする毛利一族がいずれ劣らぬ名だたる大名茶人であったことから、この地域で萩焼発祥の土壌がつくられたと言われています。
一楽・二萩・三唐津という、いつの頃からか言い慣らされてきたこの言葉は、日本の国茶歴史における優越性を端的に物語るものであり、桃山時代に千利休によって確立された「侘び茶」の流行にともない、にわかに脚光を浴びた「高麗茶碗」の系譜を引く茶陶として広く知られているところです。また萩焼の呼称は寛永十五年(1638)の『毛吹草』からと言われており、茶会記では正保四年(1647)の『松屋九重会記』で、江戸時代を通じて藩街では萩焼と呼称されており、地元の藩内では「松本焼」、「深川焼」、「三ノ瀬焼」と産地で呼び分けれれていました。一般に萩焼と呼ぶようになったのは明治以降内国博覧会等に出展するようになってからのことと考えられています。また、松本萩(萩市)、深川萩(長門市)と区別する風習も生じました。